|
 -10- -10-
⑧攻方は、攻手が複数ある時、
最も短い手順で詰めること。
このルールは、⑤⑥と同様、本手順と変化手順を
判別するためのルールですが、
少しわかりにくく、かなり誤解を生んでいます。
攻手が複数ある時といっても、
作意手順に詰む攻手が複数あれば、
ルール②の通り余詰であり、詰将棋として成立していないので問題外です。
このルールでいう「攻手」とは、変化手順の中の攻手の話です。
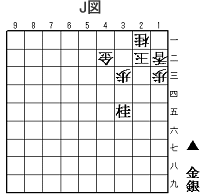
J図は、▲2三銀に対し、
(イ)△1一玉は▲2二金まで3手で詰。
(ロ)△3一玉は▲4三桂不成△同金▲3二金まで
5手で詰。(▲4三桂不成に△4一玉は▲5一金まで5手)
(イ)は3手で詰むので変化手順。
5手かかる(ロ)が本手順となります。
(▲4三桂不成に△4一玉▲5一金まででも正解ですが、
ここはE図の説明の通り△同金と取る手順を答えたいところです)
さて、ここで(イ)の変化の▲2二金に気が付かなかった解者がいて、
△1一玉に対し▲1二銀成△同玉▲2三金△1一玉▲1二香まで7手で詰めたとします。
初手▲2三銀に、△3一玉と逃げれば▲4三桂不成以下の5手で詰み、△1一玉と逃げれば
▲1二銀成以下の7手かかるので、△1一玉と逃げるのが本手順と考え、
この7手詰を解答したらどうなるか。
作意手順に詰む手が複数あれば余詰ですが、
変化手順には何通りの詰む手順があっても構わないことになっています。
そのうちの本手順より長手数の手順を「長手数だからこれが本手順」と解答されたら、
収拾がつかなくなります。そこで、このルール⑧が決められています。
このルールにより、▲1二銀成以下の手順は誤答になります。
▲2二金の1手で詰むのに、▲1二銀成以下5手もかけているので、誤答というわけです。
▲2二金でも▲1二銀成でも詰むのなら余詰ではないか、という誤解をしている人がいますが、
それは違います。
余詰というのは、「作意手順の攻手」が他の攻手でも詰むことです。
J図の場合、作意手順は「▲2三銀△3一玉▲4三桂不成△同金▲3二金まで5手詰」
(▲4三桂不成に△4一玉▲5一金も誤答ではない)です。
この▲の手(攻手)▲2三銀や▲4三桂不成が他の手で詰めば余詰です。
▲2三銀のところを▲2三金でも詰むとか、▲4三桂不成のところを▲2二金や▲3二金でも詰めば、
それは余詰です。
▲2二金は変化手順の中の攻手であり、その手に替えて▲1二銀成でも詰むのは、
余詰ではありません。
このように、変化手順の中に、受方の玉が詰む攻手が複数ある場合、
変化別詰(略して「変別」)といいます。
「変別」は、この▲1二銀成のように長手数の場合、これを本手順と誤解して、
解答してしまう場合があります。
変別手順での解答は、ルール⑧(⑨にも)に違反しているので、原則は誤答となります。
原則は「変別は誤答」ですが、現状では「発見が困難すぎる場合は審査を緩和する」等の措置が取られ、
正解扱いとする場合もあります。これは私としては違和感があります。
発見困難な手順を創るのが、作図者側の楽しみであり、創り甲斐でもあり、
その手順を発見するのが解者側の喜びです。これこそパズルである詰将棋の本質と思うからです。
以下「2016年9月11日追記」
「攻方は最も短い手順で」(「攻方最短」)のルールの意味は、以上の通りですが、
違う意味でとらえているケースがかなりあるようです。
以下の①②③はすべて、間違えた解釈と思います。
(きちんとしたルールが整備されていないので、「間違いです」と言い切れないところが、つらいところですが)
①「最終手1手で詰むのに、3手以上かけて詰ませるのは、「攻方最短」に反しているので誤答」
これは最終手余詰の話です。15ページにも書きましたが、もともと作品のキズですから、
「攻方最短」は関係なく、3手以上の手順で解答しても、「正解扱い」です。
②「たとえば作意が15手詰で、13手の余詰があったとき、
作意を解答すると、「攻方最短」に反しているので誤答」
これは「余詰」があるということ。
余詰があるのですから、詰将棋として成立していません。
「問題」が存在しないのですから、「答」もあるはずがなく、
本手順も、正解も、誤答もありません。
「攻方最短」は関係なく、解答者全員が「正解扱い」です。
③「迂回手順は、「攻方最短」に反しているので誤答」
これも14ページに書いた通り、もともと作品のキズですから、迂回手順を解答しても「正解扱い」です。
上の文中で「正解扱い」というのは、「正解」とは違います。
正解ではないが、出題側の不備なので、その解答を「正解と同等に扱う」という意味です。
(最終改稿2016年9月11日)
-10-
|